「永代供養墓」は墓地?納骨堂?<後編>
前回は、「埋葬」と「収蔵」の観点から見てみましたが、今回は、管理・運営の観点から考えてみます。遺(焼)骨をおさめる際の手統は、市町村の発行する「火葬許可証」あるいは「埋葬許可証」を受理した後でなければ、「埋葬又は焼骨埋蔵をさせてはならない(墓埋法第14条)と定められています。もし、こうした手続が当該施設のある墓地や墓園の管理書によって行われておらず、施設を有する法人や団体によって独自に行われているのだとしましょう。と、すると、そうした施設におさめられている遺(焼)骨が改葬されることになった場合を考えてみてください。墓地管理者は火葬許可証を受理していない、墓地台帳に紀録されていない、そうした遺(焼)骨について、「埋蔵証明書」を発行し得るものでしようか。分骨についても同様のことが考えられます。
ひとつの解決策、対応策としては当該法人、団体と墓地、墓園が使用関係を取り交わす際に、「遺(焼)費をおさめる場合、必ず管理者を通して行う」という約定を定めることも考えられます。しかし、こうした約定についても、墓地、墓園の管理運営の現実から捉えるなら、その履行が余程厳密に行われなければ、その施設は遠からぬうちに、管理者がおさめられている遺(焼)骨を把握し得ない状況に至ってしまう蓋然性が極めて高いといわざるを得ません。なぜなら、個人と使用間係を交わしている、いわゆる「普通の」墓所区画に設けられた墳墓においてさえ、使用者自身あるいは第三者の手によって、遺(焼)骨が無断に埋蔵されてしまうケースが珍しいことではないからです。
以上のような可能性を考慮すれば、法人や団体との使用関係を取り交わすためには、極めて特殊かつ慎重な対応が求められることになるでしょう。
なお、ここまでの議論は一墓所区画を特定の法人や団体の使用を想定して進めてきました。しかし、墓地、墓園内の区画のうち、ある程度まとまった一定数の使用権を特定の法人や団体に認める場合についても同様の間題が指摘されるでしょう。つまり、特定の法人や団体に一定数の区画を割り振る場合においても、使用関係はあくまでも当該墓地、墓園経営書側と個々の使用者との問で独立して交わされるべきものであって、法人や団体との間で交わされるべきものではありません。これを別の形で言い換えるなら、墓地、墓園側は法人や団体に対して(墓地、墓園に対する)断りもないままに、それらの区画について、個々の使用者との間で独自に使用関係を結ぶことができないことはいうまでもないということになるのです。
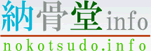





ある墓園における事例になりますが、前述の「当該施設に焼骨をおさめる場合、必ず管理者を通して行うこと」という約定に加えて、一定期間ごとに法人あるいは団体の承諾の下、管理者自身が当該施設内に立ち入り、おさめられている遺(焼)骨状況を確認することについても認めさせているというところもあるほどです。
こうした問題のほか、法人や団体が解散した場合、それらが設けていた施設におさめられている焼骨の取扱いはどうなるのでしようか。管財人もしくは精算人がこれを引き継ぎ、適切に取り扱ってくれるならよいのですが、こうした施設自体、代替性も融通性もありませんから、おそらくは放置されたままになってしまうのではないでしょうか。最終的には、墓地、墓園の管理者側によって、無縁改葬の手続きが求められることになるのでしょうが、これについても個人の使用している墳墓と同じように考えてよいのかどうか、検討しなくてはなりません。